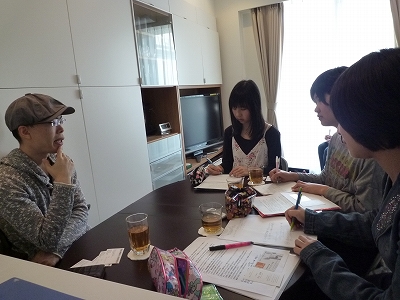澤山友佳(17)
163万人もの従事者がいながら、高校生の進路ガイドブックには決して乗ることのない仕事、農業。農林水産省の統計によると、平成22年度の新規就農者は54,570人。4年前と比較すると33%減少した。「きつい、汚い、稼げない」という ネガティブな3K がつきまとう。そんな中、新しいスタイルでそうしたイメージを打ち破る人たち がいる。
株式会社みやじ豚代表取締役の宮治勇輔氏(34)は NPO法人農家の「こせがれネットワーク」代表理事・CEOも務める。勤めていた都内の大手企業を辞め、養豚業を営む実家に戻ったのは7年前。育てた豚で バーベキューを開催すると大好評。噂は口コミで広まり、「みやじ豚」として ブランドにまでなった。現在では生産量の約5割をレストランへの卸売りやオンラインショップでの販売などの直接販売でさばき 、利益率は養豚業界トップクラスを誇る。

千葉県で梨を育てる のは實川勝之氏(32)。父の怪我を機に農家である実家を継ぐまではパティシエとして洋菓子 店で働いていた。元々栽培していた米や野菜に加え、新たに梨栽培を始めた。コンセプトは「梨というfruitsを梨というsweetsに」。目指すのはケーキのような、上品で少し特別な存在だ。そのための努力は惜しまない。試行錯誤を重ね、独自の栽培方法を編み出した。美しさにもこだわる。自身の農園を「工房」と呼び、ショーケースのように整然とした「日本一美しい梨園」と自負する。現在10種類以上を生産。購入 者 に好きな梨を見つけてもらうためだ。さらには一本の木を購入し、接ぎ木により梨をカスタマイズできるオーナー制度を導入 したり、もぎ取り体験を実施したり、客とのコミュニケーションを通して信頼関係を築く 工夫を凝らす。
農地や設備がそろ っており、親から技術指導を受けられ、周りの農家や 客 からの信用も得ているという 就農 条件が整っている農家出身者と比べると、非農家出身者はいささか険しい道を迫られる、と宮治氏は言う。だが、非農家出身者が挑戦しているケースも 少なくない。北海道でアスパラガスを栽培する押谷行彦氏(42)は この道13年のプロだ。 前職は兵庫県尼崎市にあるスーパーマーケットの従業員。大学時代、 スポーツに打ち込んでいたこともあり、「一日中エアコンが効いた 室内で働くより、 季節を感じながら汗を流して働きたい。」一念発起して憧れの北海道へ渡った。大学へ入り直して知識と人脈を得、さらに2年間農園で研修を受けた。スーパーで働いていた分、客の感覚が分かる。「平均的な価格だけど他のものより美味しい。」そのシンプルな戦術 がオンライン販売だけで多くのリピーターを生み出す秘訣だ。味で差別化を図るからには、栽培へのこだわりは半端 ではない。アスパラの太さは通常の二倍ほど。さらに、10cmほど余分に育て、出荷の際に根元の10cmをカットする。柔らかく美味しい部分だけを残すためだ。
宮治 、實川 の両氏が指摘するように、従来農業は「味に関係なく農協を通して画一的に生産物が出荷され、価格決定権がないばかりか、顧客からのフィードバックも受けることが出来ない」、「おいしいものを届けたい」という思いが評価されにくい世界だった。押谷氏を含め3人に共通するのは、一度他の業界で経験を積んでいること。独自の視点を活かして生産から販売までを一貫してプロデュースすることで、その問題を克服した。さらに、消費者と直接つながりができることはやりがいや喜びにもつながる。宮治氏は「農業は3K(かっこよく、感動があって、稼げる)産業だ」と語る。
農業従事者が減少していく今は、非農家からの就農の好機 でもある。ただし、「ブームに乗っていいイメージだけを持って来る人や、他の仕事が嫌で逃げてくる人には農業は続かない。農業は自然に左右される仕事。決められた時間働けば決められた収入が得られるわけではない 」と語る押谷氏は 。自らの 経営が軌道にのるまで5年間は辛抱が続いたという。それでも「『おいしいものを届ける』ことに喜びを感じられる人、『自然を残したい』という思いのある人なら継続できるはず」と新規就農者にエールを送る。 。「家族と触れ合う時間が持て、地域発展にも貢献 できる、そしてお客さんの喜ぶ顔を見ることができ る」と實川氏は農業の魅力をこう語る。インターネットやソーシャルメディアの発達した現代、ビジネスのスキルを身に付けた若者にとって、自然の中で働く仕事「農業」は現実的かつ魅力的な選択肢となっていくのかもしれない。